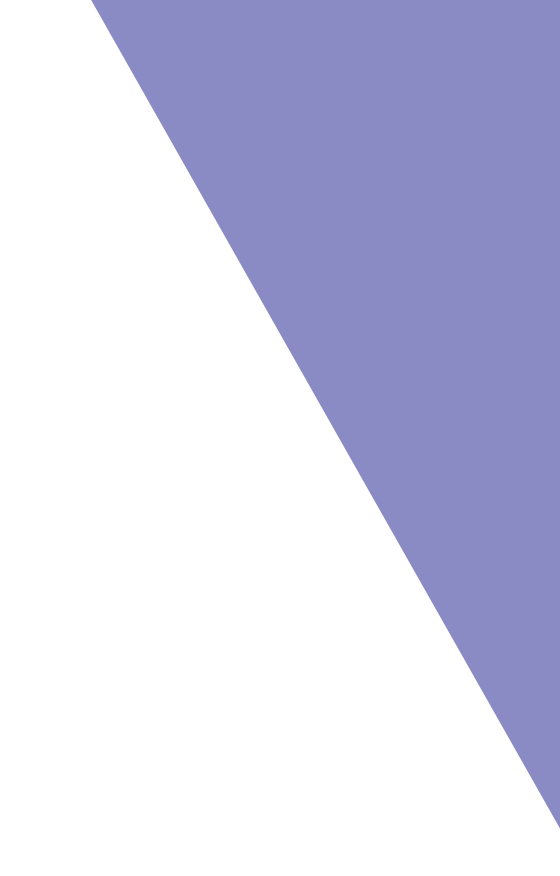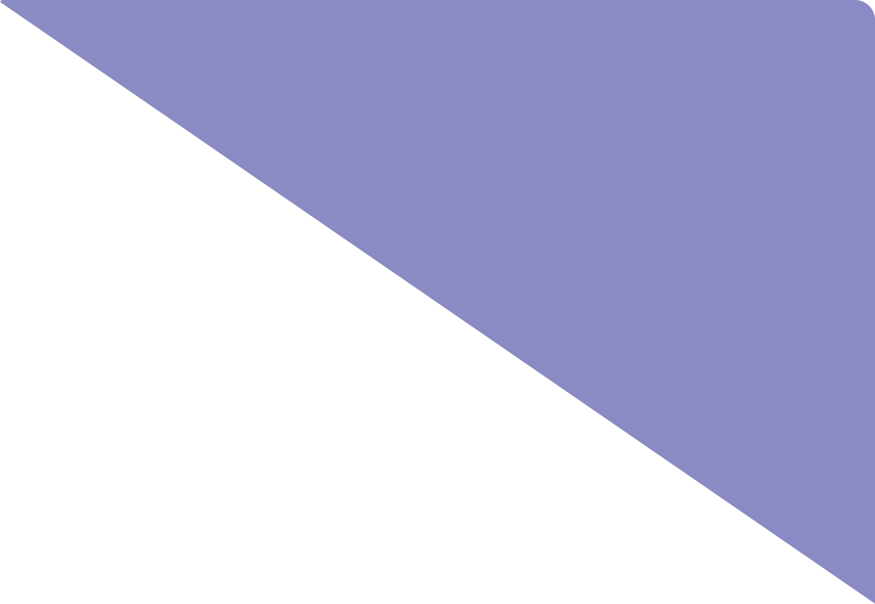友田典弘 Tsunehiro Tomoda
2つの戦争を生き延びて
3.韓国へ
韓国へ
門司港は、朝鮮半島に引き上げようとする、行李や背のうを担いだ人々であふれかえっていました。金山さんは周りの人々が、私が日本人だとわかると何をするか分からないから、「アボジ」(お父さん)という言葉以外は、ぜったいしゃべってはいけないよと言いました。私はそれ以降、船の中でもどこでも何もしゃべらず、ただ「アボジ」とだけしか口にしませんでした。その日のうちに港で、まず2,30人ずつ小さな漁船に乗せられ、沖に停泊している大型貨物船まで運ばれました。門司ではパスポートを見せるなどの検査はなく、とにかく混乱の中で次々と漁船に追い立てられていくという感じでした。監視をしていたのは、アメリカ兵でした。私たちは何百人という半島出身者と一緒にその貨物船で釜山に向かいました。船の中では、エンジンのすぐそばの船倉に板を敷いて雑魚寝です。ボンボン、ボンボンというエンジンの音がうるさかったのですが、みんなそれに負けないくらいの大声で楽しそうにしゃべっていました。母国に帰ることができる喜びと、日本が戦争に負けたことで、解放感にあふれていたのでしょう。けれども私は、周りの人々が話す言葉が、今まで慣れ親しんできた日本語ではなく、聞いたこともない言葉で、何一つ理解できず、いったい自分はどこに行くのだろうと不安になりました。
釜山には翌朝到着しました。甲板から埠頭を見下ろすと、大勢のアメリカ人憲兵が待ち構えていて、下船する人一人ずつから事情聴取をしていました。私は言われた通りに一言も口をきかず、金山さんにぴったりとくっついて片時も離れませんでした。釜山の港では、逆に朝鮮半島から日本に引き揚げようとする日本人でごった返していました。当時、門司でも釜山でも検閲をしていたのは、アメリカ兵だったと記憶しています。
釜山からソウルまでは再び貨車に乗りました。日本でも韓国でも貨車には無料で乗れました。もちろん引き揚げ船も無料でした。途中何度か検問をくぐり抜けましたが、私は彼から「一言もしゃべるな。」といわれていましたので、日本人と気づかれることなく無事通り抜けることができました。金山さんは私にキム・ヒョンジンという名前をつけてくれました。後で分かったことですが、韓国では、「行列」(ハンニョル)という習慣があり、氏族ごとに各世代の男の子につける文字が決まっています。名前を見るだけで、何氏の何代目であるか分かるのです。ですから「ヒョン」というのは、金山さんのお兄さんの息子にも、後に生まれる金山さんの息子にもつけられています。血のつながりのない私に、氏族が使う文字を使ってくれたということは、私を家族として扱うという意味だったのです。韓国の人々にとって、姓・名というのは、氏族の中での位置を示す役割があり、とても大切なものなのです。
居場所のない暮らし
ソウルの永登浦(ヨンドンポ)というところに金山さんのお兄さんの家がありました。その家には4部屋あって、金山さんと私はその一部屋に住ませてもらうことになりました。しかし、日本人を連れてきたということで、兄嫁さんと金山さんがいつも喧嘩をしていました。金山さんが留守をすると、私は兄嫁さんや息子さん(当時19歳)に殴られたり、食事をもらえなかったりしました。金山さんは「気にするな」と言ってくれましたが、とても居心地が悪かったです。当時警察が、日本人が隠れているかどうか捜査していましたし、兄嫁からすると、なぜ日本人を匿わねばならないのかという気持ちだったのでしょう。
韓国に渡って数ヶ月くらいして、金山さんとお兄さんが、私を学校に通わせようと、学校の先生に相談しました。先生は、資金援助をしてくれる人を探してくださいました。その人がどういった人なのかは分かりませんが、私は学校に行けることになりました。しかし言葉を話せないことでいじめられ、すぐにやめてしまいました。入学するときに、地方から出てきてソウルの言葉がしゃべれないと、金山さんが嘘の説明してくれていましたが、何しろ言葉が全くできませんでしたから、すぐ韓国の人間ではないと、ばれてしまいました。文字も自分の名前しか書けませんでした。日本人であることがばれてはいけないと分かっていたので、日本語で言い返すこともできませんでした。私は家に引きこもり、毎日毎日母のことを思い出して泣いていました。よく思い出していたのは、母が弟と私をボートに乗せて、川下りをしたことでした。金山さんも、それまで一滴も飲まなかったお酒をあびるように飲むようになっていました。お兄さん家族と私の間に入って、つらい思いをしていたのでしょう。
一年余りして金山さんが結婚し、ようやくその家を出ることができました。当初は新婚の二人と私の3人で仲良く暮らしていましたが、子どもが生まれると、今度は奥さんにつらく当たられ、その家にも居づらくなりました。そのころには言葉も不自由なく話せるようになっていました。
浮浪児に
1949年、13歳の時、私はとうとう毛布一枚だけを持って家を飛び出しました。それは寒い冬でした。当時、キリスト教の一派である救世軍が、何十人という戦争孤児を集め、大きな建物に収容していました。私もその中に入りました。しかし、それは仮の収容施設で、後に10人ずつほどのグループに分けられ、あちこちの地方の施設に送られるということを知りました。私はどこに連れて行かれるか分からないと知り、そこで仲良くなった子どもと3人でそこを抜け出しました。収容されてまだ一ヶ月も経っていなかったと思います。
行く当てもなかったので、大きな市場がある東大門(トンデムン)に行きました。昼間は食べ物を探して市場をウロウロし、夜は小屋や屋台の中などで「かます」(広辞苑:藁むしろを二つに折って作った袋。主に穀物、塩、石炭などを入れるのに用いる。)にくるまって寝ました。次第に活動範囲も広まり、東大門だけではなく、南大門(ナンデムン)や明洞(ミョンドン)など、大きな市場があるところをうろつくようになりました。ソウルの冬はマイナス15~6度になります。韓国の家では床下にオンドルと呼ばれる暖房が入れられていて、家全体が温かく、それだけは恋しかったです。ある夜、凍傷で右足の指がポロンと落ちて驚きました。寒さでしびれて痛みはありませんでした。今度は異郷の地でひとりぼっちになってしまったという思いを強くしました。
韓国の母
こんな時に出合ったのがヤン・ポンニョさんでした。私が着の身着のままでヤンさんの家の前で「かます」にくるまって寝ていたり、タバコの葉を巻いて売っていたりしていた時に、ヤンさんの娘さん(長女、私と同年齢)が声をかけてくれたのです。そしてお母さんに私が広島から連れてこられ、誰も知らない韓国で生きていることを話してくれました。ヤンさんも私が路上生活をしていたことに気づいていたそうです。ヤンさん自身も貧しい生活をしながら4人の子どもを育てていましたが、私の話を聞くと、「一緒に暮らしましょう。」と言ってくださったのです。ヤンさんの夫は日本軍に殺されたそうです。それでも「あなたは何も悪くないんだよ。」と優しくしてくださいました。日本の植民地時代の記憶も生々しい付近の住人からは、ひどい言葉をぶつけられることもありました。しかしヤンさんはいつも「この子には何の罪もない。」とかばってくださったのです。しかし、その生活はあまりにも貧しく、食べるものもほとんどありませんでした。主食も米ではなく麦でした。そんな中でも自分を受け入れてくださる家族に申し訳なく、一ヶ月も経たないうちに黙って家を出て、再び路上生活に戻りました。