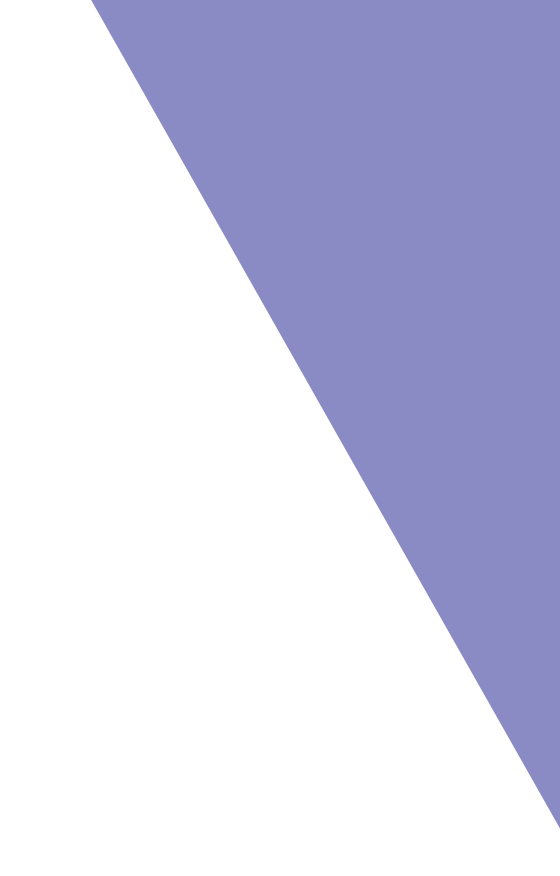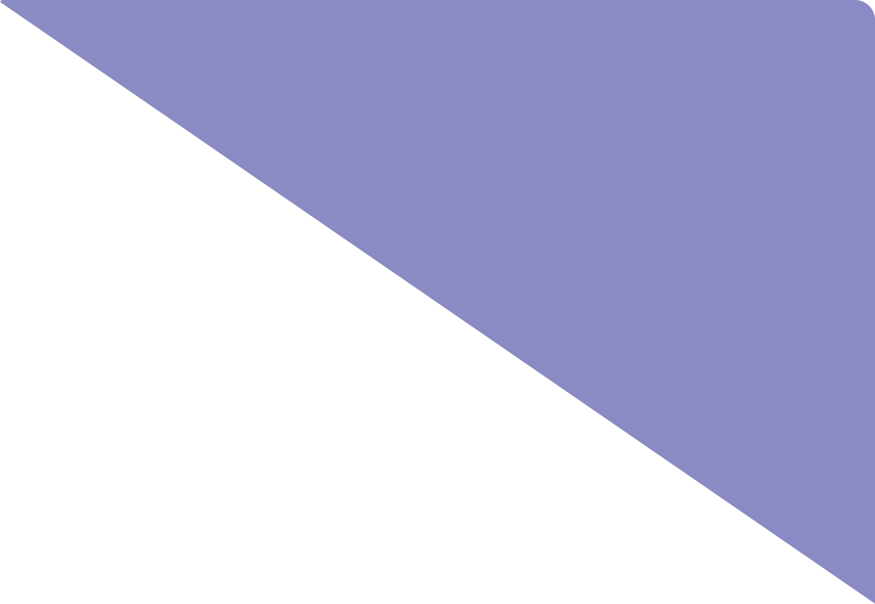川本省三 Syoso kawamoto
1.おいたちと学童疎開
おいたち

私は昭和9年3月27日に、父留一と母さつきの4番目の子どもとして生まれました。兄弟は長男・吉太郎(よしたろう)、長女・時江、次女・美智子、私、三女・幸子(さちこ)、次男・訓広(のりひろ)の6人でした。家は爆心地から380メートルの塩屋町(現在の中区大手町)で旧日銀広島支店の前にありました。
原爆投下の当時、父は51歳で退役軍人でした。恩給を得ながら、近所のガラス屋で働いていました。軍人あがりでしたが、それほど厳しい人ではありませんでした。ただ酒とタバコが好きで、物資がなくなり、配給の時代に入ると、母が苦労して手に入れていたのを覚えています。母は39歳で明るく面倒見のいい性格でした。近所の人からも「おごうさん、おごうさん」と呼ばれ、誰彼となく親しくしていました。「おごうさん」というのは、「奥さん」という意味で、当時は近所の奥さんを「おごうさん」と呼んでいたものでした。7歳年上の長男は昭和16年(1941年)、中学を卒業すると、満蒙開拓団に入りたいと両親に申し出ましたが、母から「お前は農業には向いていない。」と諭され、満州の電気会社に就職し、満州に渡っていきました。中学に来た満豪開拓義勇団の募集チラシを見て、愛国心に燃え、応募したかったようです。私たちは幼いころから学校で「人生は50年、お国のために命を捧げよ。」と教えられてきました。
兄が満州に渡った時、私は小学2年生で、兄と遊んだ記憶もありません。戦後2年目に、ようやく広島に戻ってきましたが、その6年間一度も帰省していませんし、手紙が来たかどうかも覚えていません。5歳上の長女・時江は昭和20年(1945年)3月に高等女学校を卒業し、4月から国鉄の管理部で働いていました。2歳上の次女・美智子は袋町国民学校高等科の2年生(今の中学2年生)、私は袋町国民学校の6年生、三女幸子は同じ学校の2年生で、一番下の弟訓広は4歳でした。
学童疎開
昭和16年(1941年)12月8日、日本がパールハーバーを奇襲攻撃したことで、太平洋戦争が始まりました。当初は日本軍が優勢で、戦局はどんどん拡大していきましたが、翌年のミッドウェー海戦を機に劣勢に転じました。昭和19年(1944年)の年末には、アメリカ軍がマリワナ諸島に空軍基地を建設し、そこから本土の主要都市への空襲が始まり、年が明けるとますます激しくなってきました。終戦までに空爆されたのは200都市以上におよびます。とはいえ、私達一般市民には、日本軍が劣勢に転じたことなど知る由もなく、まして多くの都市が空襲を受けていたことなど全く知らされていませんでした。大本営発表で、「敵機○○機を墜落せり。」「米艦○○号を撃沈せり。」などと見聞きし、日本軍が快進撃を続けているものと信じていました。私も含め子どもたちは「勝った。」「勝った。」と喜んでいました。憲兵の監視が厳しく、「日本軍が被害を受けている。」「もしかしたら負けるかもしれない。」などの話が人の口にあがることはありませんでした。憲兵はいつも2~3人が組になって町を巡回していました。私たちの学校にも時々やってきて、教室を覗き、先生たちがいらぬことを話していないか監視していました。学校では月に2~3度軍事教練の時間があり、兵隊さんがやって来て、竹やりの訓練などをやらされていました。
激しくなる空襲から児童を守るために、1945年4月、政府は小学3年生から6年生までの学童を、親元から離し、田舎にある寺などに疎開させることを決めました。私が通っていた袋町国民学校では、双三郡(現、三次市)にある田幸村、川西村、和田村、神杉村の4つの村に分かれて学童疎開することになりました。神杉村には、私を含め男子45人が善徳寺というお寺に、女子32人が浄現寺に疎開することになりました。先生は男女それぞれ2名ずつで、男女それぞれの子どもたちと寝食を共にしました。疎開は一学期間で、当初は7月末までで、夏休みに入ると広島に戻れると聞かされていましたが、後に8月10日まで延期されることになりました。それを聞いてみんながっかりしたものです。学童疎開に参加するためには、一学期分として一人10円が集められましたが、そのお金を払えない子どもは、広島に残りました。また親戚が田舎にある子どもたちは、縁故疎開をしました。
疎開に必要な布団や着替え、蚊帳などは、あらかじめ疎開先に貨車で送っていました。疎開当日は、ほとんど着の身着のままで出発しました。子どもたちは汽車に乗れることが嬉しくて、大はしゃぎしていました。まるで遠足にでも行くかのようでした。しかしそれも夕食のおにぎりを食べるまででした。夜になると、3年生、4年生の子どもたちが、「お母さん」「お母さん」と言って泣き始めました。それも6月ごろになると、だんだん慣れてきて、泣く子はいなくなりました。困ったのは夜になると真暗闇になることでした。音というものも一切聞こえませんでした。便所が外にあったので、怖くて行けず、男の子たちは縁側に並んでおしっこをし、朝になると匂いがとてもひどかったということもありました。中にはおねしょをする子もいて、お世話をしてくださった人は大変だっただろうと思います。
三度の食事や身の回りの世話をしてくれたのは、地元で雇われた5人ほどの女性たちでした。疎開先での食事は、小さな茶碗一杯のご飯とみそ汁と漬物だけでした。ご飯といっても半分麦が混ざったものでした。最後の方になると大豆のかすも混じっていました。その量は国で一人前一食分として米7勺(0.7合)と決めていたと聞いています。何しろ食料不足の時代でしたからね。皆、育ち盛りの年頃で、とても足りませんでした。いつもお腹をすかせていました。昼食の時間、疎開先の地元の同級生が開いた弁当箱は輝いて見えました。白い米粒がぎっしり詰まっていて、うらやましくてたまりませんでした。「おい、鉛筆やるから分けてくれよ。」「消しゴムと交換してくれや。」と、弁当を分けてもらったこともありました。小麦の穂をしごいて、手で揉んで生のまま食べたこともあります。これは噛めば噛むほど粘りが出て、なかなか美味しかったように覚えています。野草や田んぼのあぜ道に植えてある枝豆もむしって口に入れたりもしました。美味しいかどうかではありません。とにかく口に物を入れるだけで、気を紛らわすことができたのです。
美味しかったのは、トノサマガエルでした。炊事をしてくれるおばさんが月に一度ほど、「カエルを取っておいで。」と言ってくれると、みんなで田んぼに走って行って、カエルを捕まえてくるのです。子どもたちが両脚を引っ張って、つるして皮を剥いで持って行くと、炊事担当の人が天ぷらにしてくれました。鶏肉のササミに似た味で、貴重なタンパク源でした。あとは、イナゴやバッタも食べました。これは竹串に何匹か刺して、竈の熾火において焼いて食べるのです。イナゴは結構美味しかったですね。何でもありでした。イナゴも育ちざかりの子どもたちにとって大切な栄養源になりました。洗濯は週に一度おばさんたちがやってくれました。石鹸などない時代ですから、洗濯といっても川の水でザブザブ洗うといった程度でした。お風呂は5~6人のグループになり、週に一度近所の農家のお風呂に入れてもらいました。
疎開先ではほとんど勉強はしませんでした。松の幹に傷をつけて、竹筒をその下に一週間ほどぶらさげて松脂を集めたり、荒れ地を開墾してサツマイモやジャガイモを植えたり、そういう作業が勉強の代わりでした。松根油は航空機の燃料にする目的で集められていたようです。またイタドリ、ノビル、セリ、スギナなどの野草を採りに行きました。これらの野草は寺に持って帰り、乾燥させ、粉に曳いて供出するのです。
私達が疎開していた村は、最後まで面倒をみてくれたのですが、村に余裕がないところでは、最初から引き受けを拒否したり、途中で帰らせるところもありました。大竹の子どもたちは6月には帰ってきたと聞きました。また追い返すために、夜中に白い布を被った女性を便所の近くに立たせ、子どもたちを怖がらせ、とにかく帰らせようとしたところもあったようです。
子どもの中には親元に帰りたくて、疎開先を抜け出し、線路伝いに逃げる子もいたのですが、先生が追いかけ連れ戻されてしまいました。私の親は父が5月に、母が6月に会いに来てくれました。他の子どもたちも親が時々面会に来ていました。