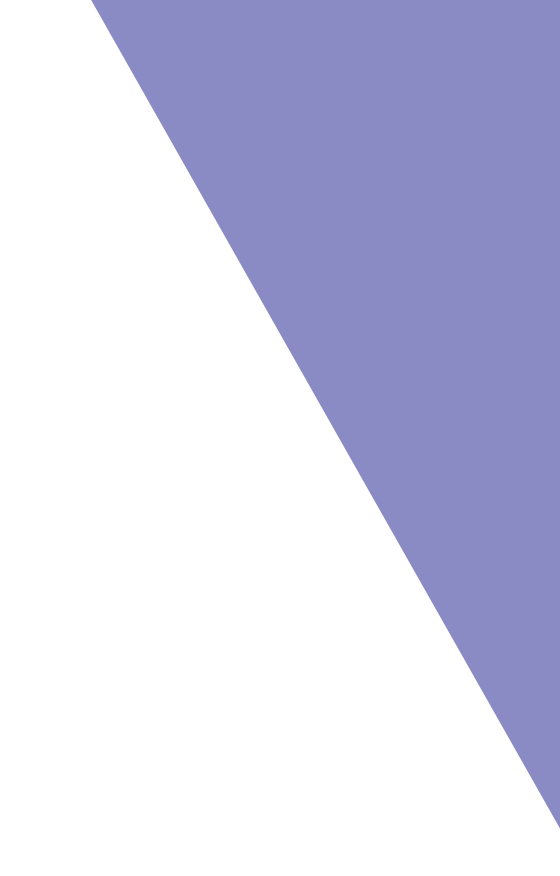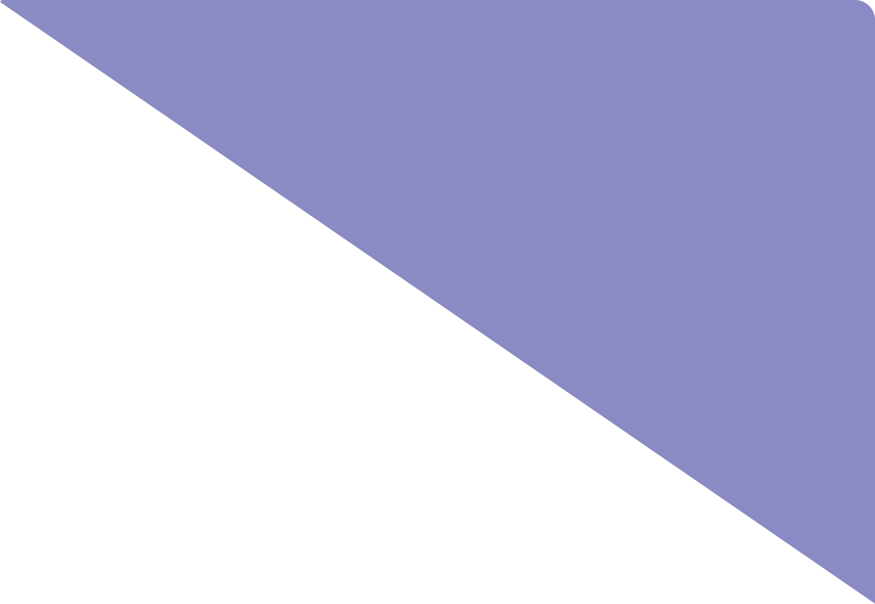川本省三 Syoso kawamoto
原爆孤児を忘れないで
5.荒れた生活を経て再出発
再び広島へ
12年ぶりに広島に戻ったある日、広島の繁華街の流川を歩いていると、突然、「川本さん!」と呼び掛けられました。小学校の一年下で、疎開先でも一緒だった孤児の「テツ」でした。彼は打越組の若頭になっており、シャツの上に腹巻を巻き、すっかりいっぱしの暴力団員でした。若い者を5~6人連れて自分の縄張りを肩で風をきって歩いていました。運転免許証を持っていた私は、彼の口利きで運送会社に住み込みで就職しました。しかし、給料日になるとヤクザの仲間からバクチに誘われました。夜になると町中をのし歩き、賭場に出入りするような生活でした。喧嘩だと聞けば竹の棒を渡されて助っ人に連れ出されていました。「叩け!叩け!」とはやし立てられ、言われるがままに相手を叩きのめしたものでした。他に友達なんて一人もいませんでした。昔の友達もみんなヤクザの仲間に入っているし、暴力団へのあこがれもあって、仲間に入れてくれと頼んだこともありました。しかし、
「お前はヤクザには向かん。優しすぎるわ。暴力団に入れるわけねえわ。」
と断られてしまいました。テツは、その2年ほど後に、新天地で刺され命を落としたと彼の手下の者から聞きました。
バクチでお金がなくなると血を売りました。当時鷹野橋にあった土谷病院で、200㏄の血液を2本1200円で買ってくれました。それだけあれば10日くらいは食べられました。月に一度くらい血を売っては仕事もせずにぶらぶらしていました。気が向いたら仕事をし、お給料をもらうとバクチを打つ、そんな生活でした。暴力団の口利きで入っていたので、私がそのようないい加減な仕事をしていても、会社は何も言わず働かせてくれ、給料も出してくれていました。
再出発
そんな荒れた生活が10年ほど続き、30歳を過ぎたころのことです。交通違反で、罰金2000円が課せられました。ところが、その2000円がどうしても工面できなかったのです。つくづく自分が情けなくなりました。人に金を借りてまで生きて行こうという気力もありませんでした。もう自分には生きる価値もない、死のうと思いました。でも広島で死にたくありませんでした。とうとうくたばったかと笑われるのが関の山です。とにかく誰も知らない町に行って死のうと、広島を出る決意をしたのです。
広島駅でポケットの中を探ると640円しかありませんでした。そのお金で買えたのは岡山行の切符だけでした。とりあえず電車に乗り、岡山まで行きました。岡山駅を出て、死に場所を探そうと歩き出した時です。目の前のうどん屋の店先の、「住み込み店員募集」の張り紙が目に入ったのです。この岡山には私のことを知っている人は一人もいない。ひょっとしたら、もう一度人生をやり直せるかもしれないと思ったのです。その時、ふと私が小さいころ、宿題を忘れた時やテストでひどい点を取った時に、母がよく私に言っていた言葉が脳裏に浮かびました。
「お前はやればできるんだよ。できないというのは、お前が途中であきらめてしまうからなんだよ。あきらめずに最後までやりなさい。」
という言葉です。心が荒んでいた時、いろいろな宗教の勧誘を受けましたが、本当に自分を立ち直らせてくれたのは、幼いころに聞いた母の言葉でした。
一念発起して、その店の中に入っていき、うどん屋の店主に頼んでみました。うどん屋は事情を聞くこともなく、
「本当にやる気があるんなら、やってみなさい。」
と、包丁も握ったことがない私を、すぐ雇ってくれました。そこで3年働き、天満屋デパートの社員食堂に移り5年働きました。そしてちょうど40歳になったころ、友人と5人で、弁当や総菜を卸す会社を立ち上げました。50歳になってから独立し、岡山を離れ、水島、倉敷を拠点とする食品会社を興したのです。ちょうどコンビニエンスストアが各地に広まり始めたころで、弁当や総菜が飛ぶように売れて行きました。社員も50人ほど雇っていました。
60歳になった時のことです。
「社長、広島からお電話です。」
と事務員が電話を取り次いでくれました。もう何十年も広島に電話をしたこともないし、手紙を出したこともありませんでした。私のことを知っている人がいるはずはないと思っていたのです。電話に出てみると、元気のいい声で
「川本、お前、生きてたんか。みんな心配しとったぞ。」
あの時、一緒に神杉村に疎開していた仲間のNでした。Nの母親は原爆投下の前日に疎開先の寺に面会に来ていて、帰りの汽車に乗り遅れ、その夜寺で一緒に寝ました。そして原爆に遭わずに助かったのです。自分の親だけが助かったことに、Nは罪悪感を抱いていました。彼は被爆50周年の慰霊祭を開くために、当時の6年生と5年生の全員の消息を尋ね歩き、6年生60人、5年生30人を探し当ててくれました。私の所在も沼田の役所などをあたり、調べてくれていたのです。私のことを覚えてくれている者がいることが嬉しくてたまりませんでした。

被爆50周年慰霊祭
「帰ってこいや。被爆50周年の慰霊祭を一緒にしようや。」
と誘ってくれました。昔の仲間の声を聞くと、懐かしくてたまりませんでした。慰霊祭をするために、25年ぶりに広島に帰った時には、みんなが本当に喜んで迎えてくれました。
その後、その時集ったメンバーで、被爆70周年になるまで20年間、鯉袋会(りようかい)と名付け年に一度集まりました。その会合で、友人たちも戦後たいへんな思いをして暮らしてきたことが分かりました。同級生だった一人の女性は、
「原爆の後、一週間ほどして母が疎開先に迎えに来てくれたんじゃけど、その時は顔中に包帯が巻かれとって、目だけが出とったんよ。私はこの人はお母さんじゃないと逃げ回って、母も私を連れて帰るのをあきらめて帰ってしもうたんよ。その後、一週間ほどして親戚の人が迎えに来て、母が死んだというんよ。私は一番の親不孝者だと、自分を責め続けてきました。」
と涙ながらに語ってくれました。
三度目の広島

2012年同窓会
私は同じ経験をした者がいる広島の地で、人生の最後を過ごそうと決心したのです。
その後、経営していた会社の整理などもあり、結局広島に戻ってきたのは70歳の時でした。広島に戻って間もなく、西区民センターで開催されたシルバーのど自慢大会に出ました。その時、司会者が私を被爆者だと紹介するのを聞いた運営ボランティアから、被ばく体験を聞きたいとお願いされたのです。その方は資料館でピースボランティアもされている人でした。
それまで当時の体験を語ったことはありませんでした。意を決してお引き受けし、証言をしました。会場は資料館の会議室で、聴衆はピースボランティアになるための講習を受けている人たちでした。
その場に、語り部として活躍されている岡田恵美子さんがおられたのです。岡田さんは私の話を聞いて、
「あなたの話は多くの人に知ってもらいたいです。一緒に活動しませんか。」
と誘ってくださいました。
ピースボランティアになるための講習を受けようと平和記念資料館に行ってみると、当時の記憶がよみがえり、足がすくんで入れず、何度もやめようかと思いました。また展示資料を見て、大きなショックを受けました。原爆関連の資料はたくさんあるのに、原爆で孤児になった子どもたちに関しては、靴磨きをしている少年の写真1枚と、「原爆孤児は2000人とも6500人ともいわれ、実態はつかめていません。」というたった一行の説明しかありませんでした。これを見た時、自分自身は原爆にあっていないのに、孤児になってしまい、懸命に生きようとした子どもたちがいたことを、もっと多くの人に知ってもらわなければならないと感じたのです。この子どもたちは家族の墓に入れてもらえることもなく、原爆死没者慰霊碑の中の死没者名簿に名前が記されることもありません。枕崎台風で流されても死者数の中にすら入っていないのです。誰からも顧みられることのない彼らのことを忘れないでほしいと、気持ちを奮い立たせ証言を続けています。
施設にも入れず、町に放り出された孤児にとって、最大の関心事は食べることでした。食べ物をどうやって手に入れるかです。孤児たちは食べられないがゆえに暴力団の世話にならざるをえなかったのです。そうした事実が消し去られているのです。暴力団を賛美するつもりは毛頭ありません。その存在を容認するつもりもありません。ただ孤児たちが生きる術として暴力団と切っても切れない関係があったという事実はなくなりません。
私は今、ピースボランティアとして活動をしています。自分が体験したこと、路上で暮らしていた孤児のことを資料館で語るようになりました。ところが、袋町小学校の同窓生から、私に非難の声が上がったのです。岡山にいた私に、広島に帰って来いと声をかけてくれた旧友たちでさえ、私の活動に異を唱えるようになりました。
仲間からの反対
私は活動に反対する仲間たちに、
「あの時は、自分が生きるために、周りの誰かを倒さなければいけなかったんだ。死んでいく友達を見ても何もしてやれなかったというつらい経験をした者もいる。現在こうして普通の顔をして生活していることに、みんな罪の意識を感じているんです。これからの若い人たちに、こうした事実を伝えようじゃないか。」
と言って、活動に誘ってみました。ところが、
「あれから60年余りが過ぎて、人は時効だと言うけど、俺たちに時効はない。あのときは憎いから相手を倒したんじゃない。生きるために仕方なくやったことなんだ。」
「今は結婚して子どもも孫もいる。子どもや孫は、私が孤児であったことは薄々知っているが、どんな生活をしてきたかは具体的に知らない。川本が話すことで私の忌まわしい過去が知られてしまう。」
「川本は家族がいなくて一人だからいい。子どもや孫のいる元孤児のことを考えろ。そんな証言は頼むからやめてくれ。」
私は原爆を理由に結婚に反対されて以来、もう二度と嫌な思いをしたくないと結婚はしませんでした。しかし他の仲間は皆結婚しているのです。子どももでき、孫もいます。
「わしは自分の子どもには話してない。あの時、どのようにして生き延びたかを。話せない・・・。まだ10歳くらいだった。助けてくれる人もいなかった。自分で生きる道を探すしかなかった。生きるためには何でもやった。他人の食べ物を腕づくで奪ったこともあった。生きるためには仕方がなかった。そうやって生きてきたんだ。」
仲間たちは、私が証言することで、それを聞いた自分の子どもたちが苦しむというのです。自分の親はそんなひどいことをして生きてきたのかと。みんな忘れたいのでしょう。その気持ちは痛いほど分かります。でも忘れることはできません。あったことをなかったことにするわけにはいかないのです。